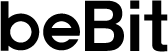あるべきDXとは ー本記事の狙い
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、新しいテクノロジーやデジタル技術を活用して、ビジネスプロセスやサービスの改善を図ることを指します。
DXは、企業の競争力向上や顧客ニーズに対応するために、今や欠かせない戦略の一つとなっています。特に2019年以降、DXはバズワードになっており、多くの企業が取り組もうとしている状況です。
しかし、現実にはDXを成功に導くことができた企業は限られており、一見成功しているように見える企業でも、本質的なDXの達成は簡単なことではありません。
本記事では、DXの本質的な意味と目的とは何かを説明し、それを実現するために必要な活動についてデータ・顧客接点・サービス開発の観点から解説します。
DXの定義と目的 ー原義と異なる日本のDX
・DXという言葉の定義
DXの定義は、スウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が2004年に発表した論文「Information technology and the good life」で提唱されたのが最初と言われています。
この論文中でDXは「デジタル技術が人間の生活のあらゆる面において引き起こす、もしくは影響を与える変化のことを指す」と定義されています。
現在の日本でDXという言葉が使われる場合、デジタル技術を用いて企業の競争力をどう変えていくかという話が多いと思います。
しかし、ストルターマン教授が提唱したもともとのDXの定義では、デジタル技術を用いることにより人間の生活全般がどのように変化するかにフォーカスが当たっているのです。
ストルターマン教授自身もDXの定義が伝わっていないことに対して2022年に社会のDX、公共のDX、民間のDXという3つのカテゴリーに分けて再定義しています。
出典:A new definition of Digital Transformation together with the Digital Transformation Lab, Ltd.
また、日本でDXの定義としてよく知られているのは、経済産業省が2018年に公開した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」における定義です。このガイドラインでは、DXの定義は以下のようになっています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
※出典:デジタルガバナンス・コード2.0(旧 DX推進ガイドライン)
この定義ではDXに取り組む企業が主語となっており、製品やサービス、ビジネスモデルを変革することでビジネスを発展させていく点に重きが置かれています。
これを見た企業のDX担当者は、競争力強化のためのDXに邁進することとなるため、ストルターマン教授が意図した「人々の生活への変化」を考慮したDXに取り組むという思考回路には、なかなかならないでしょう。その意味で、生活変化に対応させるDXに取り組むこと自体、容易ではないと言えます。
DXの目的とは ーUXを考え、提供価値のDXを実現する
アフターデジタルで提唱しているDXのあるべき姿とは、デジタルが社会に浸透したことで変化した人々の生活や行動様式に、ビジネスや提供価値を対応させることであると言えます。
デジタルとリアルの融合によって、日常の行動データが膨大に生まれたことで、人を理解する解像度が時間・状況のレベルまで高まり、同時に様々な顧客接点を通していつでも人を支えられるようになりました。この技術革新に伴い、自社がどのように顧客と関係性を構築し、どのような体験を提供するべきかを考えることこそ、DXのあるべき活動です。
したがって、UXの変革を中心に置かないDXは、中身の伴わない変革になってしまいます。
※出典:『アフターデジタル2』3-6 DXの目的は「新たなUXの提供」
日本でDXを進めるときにUXの考え方が入っていないケースが多いのが現状ですが、一方で製造業における社内業務に関するDXなど、顧客体験には直接関係のないケースもあるでしょう。こういった業務のDXと提供価値のDXは別物であり、分けて考えます。
業務のDXでは、デジタル技術を用いてコストを削減したり無駄なプロセスを無くすことによって競争優位性を確立する活動に主眼を置きます。
一方、提供価値のDXでは、デジタル技術によって変化した社会構造、生活様式、価値観などに対して、企業側も提供する価値を変えていく必要があります。
例えば、週末に自家用車でスーパーに買い出しに出かけるシーンを考えてみましょう。休日にスーパーで生鮮食品や日用品を大量に購入し、両手いっぱいに荷物を持っている人が自分の車に荷物を積み込もうとしている場面を思い浮かべてみてください。
このようなとき、荷物を持ったまま車のトランクを開けるためにはカメラの顔認証などで個人を特定してドアを開けたり、あるいはトランクの下部にあるセンサーに足をかざしてトランクを開けることができれば便利だと思うかもしれません。
しかし、もしもこのユーザーがネットスーパーで必要な商品を購入するとすればどうでしょう。両手にいっぱい荷物を抱えて困っているというシーン自体が無くなってしまいます。こうなると自動でトランクを開ける機能を開発しても意味がありません。
自動車メーカーの視点ではデジタル技術を活用した提供価値向上アイデアが見つかったように思えても、顧客の視点では不要な機能に投資している可能性があるのです。
このように、今までは自分たちの業界だけ見ていれば問題なく事業運営ができていましたが、デジタル技術の浸透によって思わぬ競合が出てきたり、今まで価値があると思っていたものの価値がなくなってしまうケースがあります。
このような状況に対応するために必要なのが提供価値のDXです。提供価値がDXされると、これまでとは業務プロセスも変わるため、業務のDXで実行する内容自体も変わっていきます。まず提供価値をDXしてから業務のDXに取り掛かる、というのが正しい順番だと言えます。
DXに取り組む企業でよくある勘違い
DXに取り組む場合によくある失敗は「とにかくデータを集めればなんとかなる」と考えてデータを活用できなかったり、「集めたデータに基づいてコンテンツを配信すれば喜んでもらえる」と考えて実行したのに顧客から見向きもされないというケースです。
ここでは、データ、デジタルサービス、顧客体験価値の3つの観点から陥りがちな失敗や勘違いについて説明していきます。
・データの話
「DXのためにデジタルを活用しよう」となると、顧客接点を通じて顧客のデータをかき集めたり、そうやって集めたデータを他社と共有して価値を生み出そう、ということになりがちです。
しかし、そのような有象無象のデータをためていっても、そのままでは過去のデータの集積でしかありません。データが大量にあれば何とかなるはず、というのは単なる幻想です。
過去のデータをどのように利用すれば価値が生まれるのか、そこまで考えてソリューションの形にしないと誰もお金を払ってくれないのです。
※出典:『アフターデジタル2』3-4 データエコシステムとデータ売買の幻想
大量のデータから価値を生み出すのはデータドリブンの企業なら可能かもしれませんが、普通の企業の場合はそのような奇跡はなかなか起こりません。
しかも過去のデータの場合は、市場環境もユーザのライフステージも異なっていることが多いため活用の余地が限られており、金融やヘルスケア以外の領域ではデータ保持にお金がかかるだけで何も価値を生まないことがほとんどです。
・デジタルサービスの話
顧客にとって体験が大事となると、新規事業としてアプリやサービスを作ろうということになりがちですが、ものづくりとサービスづくりには大きな違いがあります。
ものづくりの場合は、プロダクトをリリースして売るまでがゴールといえます。一方、サービスづくりの場合は、プロダクトをリリースして契約を結び、その後もずっと使い続けてもらうことが活動の中心です。
しかし実際には、ものづくりの観点で新しいサービスを立ち上げたあと、カネやヒトといったリソースを割いていなかったり、サービスの責任を持つ人が不在になっているケースが散見されます。
例えばせっかく作ったサービスを使い続けてもらう努力を怠った結果、新規事業の墓場となってしまうパターンや、ダウンロード数ばかりを追いかけて実際にはユーザーに使われていないパターンなどがあげられます。
インスタグラム、LINE、メルカリといった一流のサービス企業では、サービスが生まれてからずっと顧客に選び続けてもらうための努力を続けています。
一方、ものづくり企業が手掛ける新規事業ではサービスをリリースしたあとも継続してサービスグロースに取り組むケースはあまり見らません。
DXに取り組むものづくり企業は、優れたサービス企業の実例からサービス開発の手法だけを学ぶのではなく、サービスを成長させ続けるマインドセットも身につける必要があるといえます。
・顧客体験価値接点の話
つぎに、DXによって顧客が得られる体験価値について見ていきましょう。
デジタルを活用して顧客接点を大量に作ると、顧客といつでもコミュニケーションがとれるようになります。
すると、顧客に対してパーソナライズされたコンテンツをたくさん提供できるため、顧客はより多くのコンテンツを利用してくれて満足度も上がり、なんだか儲かりそうに思えます。
しかし、世の中にはすでにたくさんの情報があふれていて、自分の興味のあるコンテンツをキャッチアップすることもままならない状態です。そんなところに企業から情報を提供したところで、顧客はすでにおなかいっぱいで受け取ることはできません。
顧客にとっては、ある企業のサービスを使うに当たって「今までできなかったことができるようになる」とか「解決できなかったことが解決できる」といったことに価値があります。
したがって、企業としては「顧客にとってそのサービスや企業とつながり続ける理由とは何なのか」を自ら問い直し、定義することから、UXドリブンなDXが始まると言えるでしょう。
UX型DXのパートナー、ビービット
ビービットでは、提供価値のDXにおいても、またサービスリリース後のグロース活動においても、これまで様々な業界の企業にUX指向なDX支援を提供してきた経験があります。
2つのケイパビリティを併せ持っているからこそ、社会や生活の変化に対応する本質的なDX実現を、上流から下流にわたって横断的に支援することが可能です。
少しでもご興味のある方は、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
お問合せはこちら
レポートのご紹介
DXについてもっと知りたい、という方は、ぜひ弊社レポート「顧客志向DXの最終形 ーアフターデジタル最新理論」をご活用ください。DX推進に関わる方々向けに、ビービットが考える「DXを通して企業・事業が目指すべき、顧客体験の最終形」について解説しています。

関連記事
-
学ぶ・知る
2026.02.16 Mon.
-
学ぶ・知る
2024.05.07 Tue.
-
学ぶ・知る
2024.04.10 Wed.