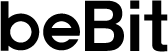CX(カスタマーエクスペリエンス)とは?
CX(カスタマーエクスペリエンス)とは、商品を買ったり利用したりすることで得られる顧客の「体験」と、その体験を通じて得られる「価値」のことです。
たとえば「車」に関するCXを考えてみましょう。まずは商品について情報を集めて、他の車種と比較検討してから購入します。購入後はドライブしたり、故障すれば購入店に修理を相談したりします。こうした一連の行為や、それによって生じた価値──モデルラインナップを見たときの期待感や、車のスペック、ドライブの爽快感、修理業者の対応に対する満足・不満など──のすべてがCXです。
ただし「CX」という語は、企業の業種・業態や社内文化に応じてさまざまに解釈されており、定義にもそれぞれ微妙な違いがあります。
また、ビービットではCXではなく「UX」の方がより広く、かつ今後さらに重要になっていくと考えていますが、両者が区別せずに使われている場面もしばしば目にします。CXとUXは何が違うのか、なぜビービットではUXが重視されているのかについては、本記事の最後に改めて説明します。
CXの向上がなぜ重要なのか ー良い利益、悪い利益
顧客が製品・サービスを利用する理由はさまざまです。CXに満足して使い続けている場合もあれば、不満はあるものの他に候補がないため仕方なく使っているという場合もありえます。
したがって、仮に多くの売上を得ていたとしても、顧客が体験に満足しているとは限りません。
顧客ロイヤルティの計測指標として知られるNPS®(ネット・プロモーター・スコア)を考案したフレッド・ライクヘルド氏は、こうした状況を “Good Profit, Bad Profit” という言葉で整理しています。
顧客に満足のいく体験を提供することで得られた利益が “Good Profit”(良い利益)、体験の質は悪いが他に選択肢がないため得られている利益が “Bad Profit”(悪い利益)です。
「悪い利益」で売上をまかなっている企業の場合、より良いCXを提供する競合他社が他に現れれば、顧客はすぐそちらに乗り換えてしまうでしょう。売上は一瞬で大きく減少します。
一方、期待以上の素晴らしい体験が得られたならば、顧客はその企業・製品・サービスのファン(ロイヤルカスタマー)になります。「良い利益」は、競合他社が現れても安定して獲得し続けることができるのです。
このようにCXの向上は、ロイヤルカスタマーと「良い利益」を企業にもたらしてくれます。
CX向上に向けた取り組みのポイント
CXの向上が他社に対する競争優位性に繋がることを確認しました。では、実際に向上させる際にはどのような点に気をつければいいのでしょうか。
ポイントは大きく分けて2つあります。1つ目が「指標を明確にする」こと、2つ目が「組織全体で改善に取り組む」ことです。それぞれ詳しく解説しましょう。
指標を明確にする
CXは目で捉えることができません。そのため改善に向けた活動の際には、指標を明確に設定する必要があります。
以下では「定量分析」と「定性分析」の2つに分けて、CXの改善に有用な指標の代表例をご紹介します。
■定量分析
定量分析とは、数値化したデータを分析・評価する手法です。
代表的な指標としては、NPS®やLTV(顧客生涯価値)、チャーンレート(解約率)などがあります。一般的に、CXが良ければNPS®・LTVは高くなり、解約率は下がります。
ただし例外もあります。例えばNPS®の場合、知名度の高い商品・サービスであれば「あえておすすめしない」という回答が多くなることもあります。
定量的な指標ばかりを信じ込んでしまうと、実態とは異なる結論に辿り着いてしまいます。製品・サービスに合わせた指標に調整しつつ、このあとご紹介する定性分析も併せて活用するのが良いでしょう。
■定性分析
定性分析では、数値化の難しい質的なデータを分析・評価することができます。
代表的な手法としては、行動観察やユーザインタビュー、自由回答形式のアンケートがあります。顧客が自社の製品・サービスからどのような体験を得ているのか、どのような価値を感じているのかを知ることができます。
定性分析を行うことで、企業側では想定していなかった顧客の不満や意見が見つかる場合もあります。そうした発見は、製品・サービスの改善や新規ビジネスの立ち上げに役立てられます。
ただし、顧客が要望を上手く言語化できない場合もあるため、調査や分析は慎重に行わなくてはなりません。
組織全体で改善に取り組む
業務効率化の観点から、タッチポイント(顧客との接点)ごとに担当部署を分けている企業は珍しくありません。しかし、部署ごとに別々で各タッチポイントのCX改善を進めてしまうと、顧客への対応やそこで提供される体験はちぐはぐになり、体験の質を大きく低下させる原因になります。
実はCXの課題の大半は、接点間の「つなぎ」で発生しています。契約の申し込みまではスマートフォンで簡単にできたのに、最終的な契約時には紙の書類に手書きすることになってしまえば、顧客も不満を持って当然です。
質の高い体験を提供するには、部門間の垣根を取り払い、企業全体で一貫したCXを提供する必要があります。
タッチポイント全体で一貫した体験を提供するには、「カスタマージャーニー」が役立ちます。各接点で発生するやりとりや、顧客の期待・感情・行動を書き出したものです。
その際、接触から購入まで何もかも順調に進むような、企業に都合のいい「妄想ジャーニー」を作ってはいけません。ジャーニー全体に潜む顧客の悩みや困りごと(ペインポイント)を考慮に入れたうえで、それを解消するような体験設計を考えましょう。
カスタマージャーニーについて詳細が知りたい方はこちらをご覧ください。
カスタマージャーニー、アフターデジタル時代で変わる設計思想
CXとUXの違い
顧客とユーザの違い
最後に、冒頭で言及したビービットにおけるCXとUXの区別、つまりは顧客とユーザの区別についてご紹介します。
一般的に「顧客」というと、ある製品・サービスのエンドユーザ(特に購入した相手や潜在的な購入層)を指します。しかし現在、企業が考慮すべきステークホルダーは顧客だけではありません。
例えば、デリバリーフードのアプリの利用者にはどのような人がいるでしょうか。注文した商品・サービスを最終的に受け取る顧客はもちろん、配達員にも専用のアプリが支給されます。
配達員用のアプリが使いづらいと、配達の効率が下がり、得られる報酬も低くなります。他サービスへの乗り換えも充分に考えられるでしょう。デリバリーサービスを支える配達員の数は企業にとって死活問題です。配達員が足りなくなれば、必然的に配送の時間がかかり、エンドユーザの体験も悪化します。この観点からも、配達員がより使いやすく快適に配達や生活ができるアプリにするよう、十分な企画と絶えまない改善が求められます。
このように昨今のビジネスでは、顧客ではないステークホルダーの体験価値も重要になっています。しかしCXという表現ではもっぱら「顧客」の体験にフォーカスしているため、このことを見落としてしまいかねません。そのためビービットでは、そうしたステークホルダー全員をシステムの利用者=ユーザと見なし、「UX」という言葉を使うことにしています。
「CXはUXより広い概念だ」という考え
ここまでの説明に違和感を覚えた方もいるかもしれません。というのも、「CXはUXよりも広い概念だ」というイメージが広く共有されているためです。こうしたイメージが普及していったのには、歴史的な背景があります。
先に登場したのは「UX」でした。1990年に刊行されたドナルド・アーサー・ノーマン氏の著書である『誰のためのデザイン?―認知科学者のデザイン原論』での言及が初出とされています。インターネット黎明期にあって、「UX」という語はもっぱら「デジタル領域における体験」を指す言葉として受け入れられました。しかし、当時の経営層たちの心はそれほど動かなかったようです。というのも、当時はまだリアル領域における体験の方が重視されていたからです。
一方、2000年代に入ると商品だけで企業やサービスを差別化することが難しくなってきた中、どのように「より良い体験を提供して選んでもらうか」が焦点になり始めました。この流れを汲んで、経営コンサルタントを中心に、デジタルではない領域での体験を扱うようなソリューションが提唱され、リアル店舗での接客やVOC (Voice of customer、顧客の声) への対応、顧客満足度やNPS®の向上など、リアル領域での体験にフォーカスした大規模な市場が作り上げられました。実際に市場として大きく立ち上がってきたのは、デジタルタッチポイントを使って顧客の声や行動を回収しやすくなったタイミングである2010年以降かと思います。
こうした市場を総括した呼び名こそ、この記事で扱ってきた「CX」です。
つまりCXとは当初、UXを越えた先にある新たなビジネス領域として考えられていたのです。「CXはUXより広い」という考えは、こうした経緯に由来していると考えられます。
顧客にとどまらないステークホルダーへの体験価値追及
しかし、CXという言葉は「顧客」に向いている結果、接客やVOC、満足度やNPS®など、接遇・おもてなしに偏る傾向にあります。それに対して近年では、さまざまなステークホルダーが絡んだり、デジタルを含む多様なタッチポイントの利用価値・体験価値を問われたりするシーンも増えています。
デリバリーアプリで食品が届き、ペイメントアプリで支払いを済ませ、ネットバンキングで口座残高を確認するというように、デジタル接点が私たちの生活の隅々まで浸透していることに気づかされます。
ビービットでは、このようにデジタルがリアルの生活をまるごと取り込んだ世界観を「アフターデジタル」と呼んでいますが、これがCXとUXの考え方にも応用されています。リアルの接点を優先して「CXはUXより広い概念だ」と語ることは、もはやできなくなっているのです。
こうしたデジタル接点の普及は、先述したデリバリーサービスのアプリが好例ですが、ステークホルダーの多様化にも繋がっています。そうしたステークホルダーをシステムの「ユーザ」と考えるなら、むしろユーザのなかに顧客が含まれることになります。
これからの企業の成長は、顧客だけに留まらないステークホルダーたち=ユーザ全員に、高品質なUXを提供できるかどうかにかかっている──ビービットではそのように考えています。
株式会社ビービットではこうしたUXの改善活動を「UXグロースモデル」と呼び、ビジネスが体験化・コト化していく今の時代の中で最も重要な企業活動の1つであると位置づけています。UXグロース活動の具体的な内容につきましては事例ページや資料にてご紹介しておりますので、こちらもぜひご覧くださいませ。
弊社の支援実績・事例一覧
【参照記事】実績・事例ページを閲覧する
事例・ノウハウの資料一覧
【参照記事】資料ダウンロード
関連記事
-
学ぶ・知る
2024.04.10 Wed.
-
セミナー・イベント
2024.01.16 Tue.
-
学ぶ・知る
2023.06.16 Fri.